- 2025年5月19日
「立てば芍薬、座れば牡丹」には意味がある?|花と漢方にまつわる面白い豆知識
先日、スタッフから「長谷牡丹園がちょうど見頃で、芍薬も咲き始めていましたよ」と教えてもらいました。
「えっ、牡丹園に芍薬もあるの?」と不思議に思ったのですが、調べてみると――これがとても興味深い話だったのです。
実は、牡丹の栽培には“芍薬の力”が必要なんです。
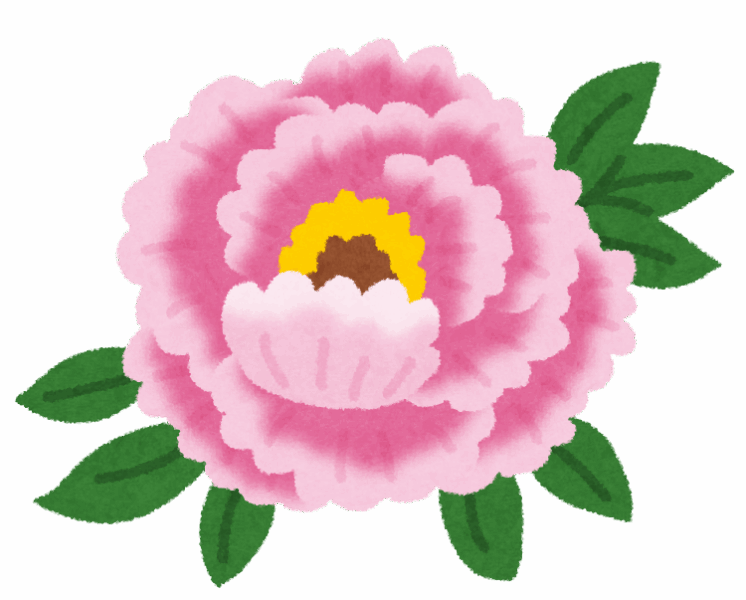
牡丹は成長がゆっくりで、種から育てると花が咲くまでに5〜10年もかかることがあります。そこで登場するのが、成長が早く根が丈夫な芍薬。芍薬を「台木」として土台に使い、その上に牡丹を接ぎ木して育てるのが一般的な方法なのだそうです。
どちらもボタン科ボタン属という近縁種なので相性もバッチリ。芍薬は、いわば牡丹を支える「縁の下の力持ち」なんですね。
そんな芍薬と牡丹は、漢方の世界でも深い関わりがあります。
「立てば芍薬、座れば牡丹、歩く姿は百合の花」――この有名なことわざは、美しい女性の姿をたとえたものとして知られていますが、実は漢方の効能の違いを表現したものだという説もあります。
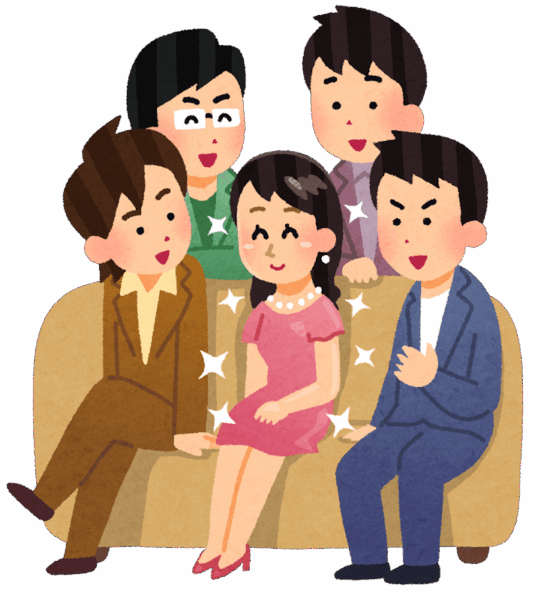
- 「立てば芍薬」は、イライラして気が立っているときに芍薬がよく効くこと
- 「座れば牡丹」は、血の巡りが悪く、動きが鈍くなったときに牡丹皮(牡丹の根の皮)が有効であること
- 「歩く姿は百合の花」は、心身のバランスを崩してふらつく状態(心身症)を表していると言われています
実際、婦人科でよく使われる代表的な漢方薬にはこれらの生薬が含まれています。
例えば「婦人科三大処方」として知られる以下の薬は、体質や症状に応じて使い分けられます。
- 当帰芍薬散(とうきしゃくやくさん):体力がなく、冷えやすくむくみやすい方に
- 加味逍遙散(かみしょうようさん):イライラや不眠、のぼせなどストレス症状が気になる方に
- 桂枝茯苓丸(けいしぶくりょうがん):血行が悪く、肩こりや生理痛がある方におすすめ
また、こむら返りの特効薬として知られる**芍薬甘草湯(しゃくやくかんぞうとう)**も、足がつる時などに広く使われており、ドラッグストアで見かけることも多いですね。
このように、芍薬と牡丹は「花」としての美しさだけでなく、「生薬」としても非常に奥深い存在なのです。

せっかくなら、この季節に芍薬や牡丹の花を楽しみながら、自然の恵みについて思いを巡らせてみてはいかがでしょうか。
ちなみに、今年の長谷牡丹園(宝塚市)の開園は5月25日(土)までだそうです。
今がちょうど見頃のようですので、お時間がある方はぜひ足を運んでみてくださいね。心と体のリフレッシュにもぴったりの散策コースです。
